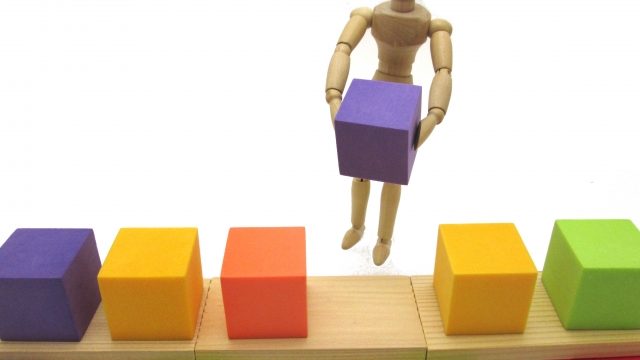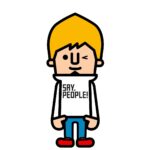目次
問題発見とは?
問題発見には、2種類あります。
1.すでに起こっている問題
2.今後起こるであろう問題
「あなたの会社の問題点を一つ上げてください。」
と言われたら、何を思い浮かべますか?
どこの会社も大体同じような問題が上がると思います。
今起こっている問題はなんですか? → 出した答えが問題です!
これが問題発見です。
早速ですが具体例を見ていきましょう。
・新規獲得に手が回らず、既存顧客にばかり手がかかっている。
・価格競争で客単価が下がってきている。
・情報共有ができておらず、二度手間が多い
・商品はいいけど、適切なプレゼン資料がない
・評価制度が曖昧で上司の主観になっている。
これらは、すでに起こっていて、目に見えている問題です。
「見えている問題」と「見えていない問題」はセットです。
以下に今後起こるであろう問題を記載しておきました。
・新規の売上構成比が低くなり、ジリ貧になる。
・客数を獲得するために広告費が上がる。
・責任者が曖昧な状態に陥り、業務フローがブラックボックス化する
・営業の機会損失を招き、無駄な人件費が増える
・好き嫌いで給料が決まっているという錯覚が起こる
どちらも言い方を変えただけで、ほぼほぼ似ている問題です。
そのため、今後出てくるであろう問題は一旦おいておいて、今起こっている問題にフォーカスしましょう。
それが問題なら、これも問題になる、これも、あれも、、、、そもそも本来は・・・と問題をどんどん大きくしていく人がいます。問題は一気に解決出来ないので、一旦スルーしましょう。
次は、発見した問題を、掘り下げて、問題点の絞り込みです。
発見した段階では、何が問題の本質で、何を解決したらいいのか不明確な状態です。
問題を解決するためには、発見した問題を掘り下げて、
「これが問題だ!」と問題を特定しなければいけません。
問題の特定とは?

問題を特定する方法は2つです。
1.発見した問題を分解する
2.具体例を一つ出す
この時のポイントは
ということです。
先ほどの具体例をもとに、発見した問題を分解してみます。
「新規獲得に手が回らず、既存顧客にばかり手がかかっている。」
分解すると、問題は2つあります。
→新規の売り上げが少ない
→既存顧客に手がかかる。
特定するための考え方:具体例を一つに絞り、数値化する
新規の売り上げが少ない
・新規を獲得するもっとも重要な行動を一つ上げる
・その行動を数値化(回数・時間)にする
・その行動を実現するために何をするか?
既存顧客に手がかかる
・既存顧客で最も多い対応は何か?一つ上げる。
・その対応は何件、何時間かかっているのか?
・対応方法を変えて短い時間、少ない回数に出来ないか?
このように、より具体的な内容に分解していきます。
この作業が問題を特定するということです。
・管理不足 → 何を支援すればいいのか?
・教育不足 → 何が出来ればいいのか?
・情報共有不足 → 何を知ればいいのか?
・検討不足 → 何を決めればいいのか?
これらのNGワードは具体的に問題を特定しているわけではありません。問題発見レベルです。そこを掘り下げないと意味がありません。何が問題なのか、掘り下げて明らかにしていきましょう。
問題の解決方法
いよいよ問題解決です!
問題発見→問題特定→問題解決!という流れです。
1.起こっている問題を抽象的に捉える
2.問題を具体化する。
3.具体化したことを一つずつ取り出す
4.一つずつ具体的な解決方法を出す
問題解決のポイントは、一つずつ解決するということです。
いつまでに、誰が、何を、どのくらい、何時間、何回、どのように、を決めていきます。
例えば、管理不足という問題があるとします。
管理不足で起こっている問題の具体例を一つ挙げます。
営業の行動管理が出ていない。
行動管理とは?具体的に何のこと?
トークの内容や、案件の進捗など
つまり、具体的にはどういうこと?
という具合に、掘り下げていきます。
また、考え方として捉え方を変えるのも一つです。
管理不足とは?
制御不足、把握不足ではなく、支援することだと捉えてみて下さい。
管理不足とは、部下に対する支援不足のことです。少し視点を変えることで、具体的に、何を支援したらいいのか?が解決策の手掛かりになります。
・頑張る → 行動内容は?
・責任感を持つ → 誰が何をやる?
・気を付ける → 変更する手順は?
・努力する → 何時間やる?
・強化する → 回数?時間?何を?
・ちゃんとやる → 誰にチェックしてもらう?
・しっかりやる → いつまでに?何を?
問題解決の方法は無数にあります。
・人を採用する、外部へ委託する、手順を変えるなど、様々な方法を視野に入れて解決に望みましょう。
問題に気付く力

問題発見、特定、解決と進みますが、問題に気付ける人が一番素敵です。
問題に気付くポイント
がポイントになります。
何気なくやっていることでも、本来の目的を考えると、目的と行動が一致していない場合があります。
例えば、テレアポを1時間に15件コールと目標を決めているとします。出来るだけ早く話を終わらせて、コールをしていくと、押すべきところで、押せず、下手下手に出て、早く電話を切ってしまいます。そうなると、ただ、コールして回数をこなしているだけになります。
本来の目的は、アポイントを取ることです。その指標として、1時間に15件くらい電話出来たら、3時間に1件アポが取れる。ということです。
本来の目的:アポイントを取ること
勘違い行動:1時間に15件コールして回数をこなす
回数をこなしているだけだと、本来の目的と、15件コールがずれてきます。くらいつくところは食らいつき、見込みの薄いところにダラダラ時間をかけない。そういう動き方が必要になります。
今日から出来ることは、勘違い行動の発見です。
社内で、何気なくやっている勘違い行動を見つけてみましょう。
・問題を発見しただけでは不十分
・問題は具体例まで掘り下げる
・問題を特定するまでは解決策を出さない
・解決策は一つに対して一つ
・一つ崩したら他も解決しやすくなる
・問題を一気に片付ける意味はない
・一気に片付けた問題は後で問題が起こった時対処しずらい
・抽象的な言葉で解決策を出さない
・抽象的な言葉は便利だけど解決策を生まない
・本来の目的と指標が繋がっているか確認する
・目的に合わせて目標数字は変更する
・行動は数値化出来る
・失敗は手順化出来る
・気持ちには共感できる
・管理は支援
・教育は出来ることを増やすこと
・無理にロジックツリーにする必要はない
数値化するのが苦手な人へおススメ
どこまで数値に出来るのかわかります!
計算が苦手な人でも、どこまでどんな手法で数値化するのか考え方の勉強になるのでおススメです。