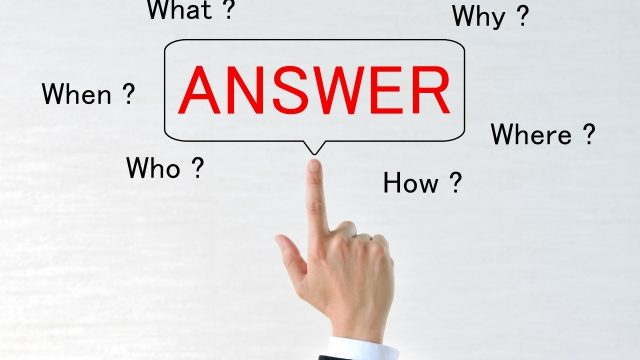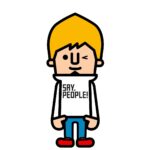目次
会議の効率の良い進め方!
会議を効率よく進めるためには、最初に会議の流れを作ることが重要です。
まず会議の目的を明らかにし、メンバーの共通認識を一致させ、スムーズな意見交換を行えるようにします。最後に、やるべきことをタスク化して会議を終了します。
会議の大まかな流れは3つです。
1.序盤 1割
2.中盤 7割
3.終盤 2割
1~3でそれぞれ、やるべきことをやると会議は効率よく進みます。
・会議の目的が不明確
・メンバー同士の共通認識がバラバラ
・会議の中盤で「そもそも論」を話し出す
1.会議の序盤は共通認識を作る
序盤は会議全体の1割を占めます。目安:60分の場合5~6分程度
序盤では、会議の概要を説明します。
概要とは(予定時間、会議の目的など)
冒頭から長々と話をしてはいけません。ここでは、意見出しもしませんし、自分の考えも発表しません。あくまで、この会議をスムーズに進めるためにメンバー全員と共通認識を作るための時間です。
「今から、会議を始めます。終了時刻は15時の予定です。まず初めに、私から5分程度で、会議の概要をお伝えします。そのあと、〇〇について意見出しを行っていただきます。」
「終了予定の15分前である、14時45分には、意見を取りまとめて、誰が何をいつまでにやるのか、明らかにし、次回の会議の開催日を決めて解散となります。」
「ここまでで、何か質問などはありませんか?」
~~~ここまでで 1~2分程度~~~
「では、私から本題の説明を3分程度で説明させていただきます。」
「今回集まっていただいたのは、〇〇に関する◐◐を取りまとめるためです。」
現状としては…このような状況です。
しかし、本来は…という状態が理想です。
このギャップを埋めるための施策として…という意見が上がっています。
この施策で行くのか、他の施策で行くのかも含めて、誰が、いつ、何をするのか?を決めて進めていきます。
~~~ここまでで 5~6分程度~~~
上記の具体例のように、会議の序盤では、会議の予定時間、会議の目的を説明します。メンバー全員と共通認識を最初に作ることで、会議の流れがスムーズになります。
事前に資料などを把握しておくと、更にスムーズに会議を進められます。
2.会議の中盤は問題点を明らかにする
中盤は会議全体の7割を占めます。目安:60分の場合40~45分程度
中盤では、会議の本題について意見交換を行う場です。
意見交換は、施策を実現するために障害となる問題点を明らかにするために行います。そのために、各部署のリーダーや、主要メンバーと言われる人達に会議へ参加してもらっています。
「その場合、〇〇のデータ管理が出来ていない状態です。」
「それは、こちらの部署で何とかできそうです」
「そうすると、案内をこのように変更する必要があるので、通達文とマニュアルを作成しないといけないです」
「以前使っていた雛形があるので、それを書き換えれば、早くできそうですね」
「では、その雛形を私に送っておいて下さい。」
「仮に出来たとして、〇〇という問題が出てきそうですね」
「その場合は一度調査が必要ですね。」
「では、次回の会議までに調べておきます」
このように、問題点を次々に出していき、メンバー同士で意見交換を行います。
その場で解決策が出ればいいのですが、解決策がでないものは、その場で話し合うのではなく、持ち帰りで調査を行います。
ある問題があるとします。
解決出来るのかどうかが判明しなければ、これ以上話合いが進まない、話合いをしても意味がない。という状況が稀にあります。
その場合は、会議開催前の準備不足が原因です。明らかに大きな問題や、それが解決しなければ話合い自体が進まないような事柄に関しては、別途担当者同士で進めてから会議を行った方がいいでしょう。
3.会議の終盤は問題点をタスク化する
終盤は会議全体の2割を占めます。目安:60分の場合10~15分程度
終盤では、誰が、いつ、何をやるのかタスクを決めます。
また、次回の進捗確認日も決めます。
| タスク名 | 担当者 | 期日 | 進捗報告日 |
| 〇〇の調査 | Aさん | xx月xx日(仮) | xx月xx日 |
| 〇〇の作成 | Bさん | xx月xx日 | xx月xx日 |
| 〇〇の比較 | Cさん | xx月xx日 | xx月xx日 |
上記の表のように、タスクをまとめます。
まとめたことは、参加者にも共有します。
相手の会社の都合などで、期日が読めない場合でもxx月xx日(仮)として期日は必ず設けます。また、各担当者は、確認日の2日前にはタスクが完了している状態にし、前日には、会議で報告出来る資料や話の流れ作っておきましょう。
・序盤で共通認識を作る
・中盤で問題点を洗い出す
・終盤で期日と担当とタスク内容を決める
・進捗の報告日を決める
会議の役割分担について

会議を効率良く進めるには、役割分担も必要です。
どのような役割が必要なのか説明します。
議長が一人ですべての役割りをこなしてもいいですが、役割は3つあります。
・議長
・タイムキーパー
・議事録係
これら3つの役割が会議で発揮されると、会議は非常に効率よく進みます。
逆にこれらの役割りが発揮されなければ、グダグダな会議になってしまいます。
・議長が序盤で流れの説明をしない
・中盤に議長が積極的に話をする
・タイムキーパーが時間のお知らせしかしない
・議事録係がメモを取っているだけ
議長の役割りは進行役
会議には進行役が必要です。
複数人が参加しているため、会議の方向性をコントロールしなければいけません。
そのために必要なのが議長です。
議長というと、積極的に話しているイメージがありますが、違います。
議長が話をするのは、最初の5分程度です。
中盤~終盤にかけてが仕切り役としてメンバーに質問を投げかけるのが議長の役割りです。
「今でた課題はどなたが調査しますか?」
「どのくらいの仕事量が必要ですか?」
「期日はいつ頃になりますか?」
「いくらくらい費用がかかりますか?」
「作成するために必要な情報はなんですか?」
会議の参加メンバーから出た意見に対して、「何を、誰が、どのくらいかけて、いつまでに」完了するのかを質問しながら明らかにしていきます。スムーズに質問することで、会議の方向性をコントロールし、時間短縮を行います。
タイムキーパーは話を遮る権限を持つ
タイムキーパーは人の話を途中で遮る権限を持つ人です。
会議は開始時間と終了時間が決まっています。時間内で会議が終わるようにするのがタイムキーパーの役割りです。決して時間を図ってお知らせする係ではないので注意しましょう。
・脱線したら本題へ話を戻す
・同じ発言を繰り返す人を抑制する
・1回1回の話が長い人を抑制する
確認です。この後のお話しされる流れは、先ほどと同じ内容ですか?
質問です。つまり、〇〇という意見でお間違いないですか?(要約して質問する)
提案です。確かに重要な問題ですが、本題とそれますので、別日程でお願いします。日程は会議終盤に決めましょう。
ちょっとすみません、意見がすぐ出ないのであれば、次の方からお願いします。
タイムキーパーはメンバーが話をしている途中でも話を遮る権利を持っている唯一の参加者です。揉め事を避けるためにも、そういう立ち位置の人だということは会議前に周知しておきましょう。また、話を遮るのは気が引けるものです。合言葉を決めておくとスムーズです。「ちょっとすみません」「質問です」「確認です」「提案です」など、話だしを決めておくと遮りやすいです。
議事録係の役割りはタスク化の確認
議事録係は会議で出た意見に対して決まったことと、決まっていないことを周知する役割があります。その結果、メンバーが迷わず行動出来るようになります。
そのため、会議で出た意見をまとめたり、話をメモするだけでは役不足です。
会議の途中で、本来の目的からズレていないか?、問題点に漏れはないか、タスクにダブりはないか?などを議事録を取りながら確認しなければいけません。
・序盤で〇〇という目的でしたが、〇〇さんの施策は相反するところがありませんか?
・中盤で〇〇という問題がでましたが、どなたが担当かまだ決まっていません。
・中盤で〇〇をやることは決まりましたが、期日が決まっていません。
・終盤で出た〇〇の調査ですが、〇〇と被っていませんか?
会議の議事録を確認しながら、漏れがないか確認します。終盤のタスク化の際、何が決まっていて、決まっていないことは何なのかを発表して、メンバーに確認を取ります。すべて確認が取れたら、タスク化したことをメンバーへ共有します。
メンバーは会議が終わったあと、安心してタスクへ取り組むことが出来るようになります。
・議長は発言を控えて、質問に徹する
・タイムキーパーは話を遮る権限を持つ
・タイムキーパーの役割りは事前に伝えておく
・タイムキーパーは合言葉を決めておく
・議事録係はメモではなくタスク漏れを防ぐため。
・議事録係はタスク化したことをメンバーに共有する